「最近、子どもとおじいちゃん・おばあちゃんが一緒にいる時間が減っている気がする…」そんなことを感じたことはありませんか?
日常の忙しさの中で、家族全員が揃う時間を作るのは簡単ではありません。ましてや、世代の違う家族が一緒に楽しめるものを見つけるのは一層難しいものです。
そこでおすすめしたいのが「絵本」です。
絵本は、単に子どものための読み物ではありません。大人も楽しめる深いメッセージが込められたものや、昔懐かしいお話を再体験できる作品もたくさんあります。
おじいちゃん・おばあちゃん世代が声に出して読むことで、子どもたちにとっては特別な思い出になり、親世代もほっと一息つける貴重な時間になるのです。
絵本は、親子三世代が一緒に楽しめる「時間の架け橋」になります。
本記事では、おじいちゃん・おばあちゃんが楽しめる絵本の選び方やおすすめ作品、またそのメリット・デメリットについて詳しく紹介していきます。
おじいちゃん・おばあちゃんと絵本を楽しむのは難しい?

世代間ギャップが生む絵本の壁
「絵本は子どもが楽しむもの」と思い込んでいるおじいちゃん・おばあちゃんも多いかもしれません。確かに昔は、子どものためにだけ作られた絵本が主流でした。
しかし、現代の絵本はその枠を超え、大人も楽しめるストーリーや深いメッセージ性を持つものが増えています。
それでも、「子ども向けの本を読んでも面白さがわからない」「内容が単純すぎて退屈に感じる」と感じる方も多いのが現状です。
また、文字が小さい・色使いが派手すぎるなど、視覚や聴覚の感覚が年齢とともに変化しているために「読みづらい」と感じる方もいます。
このような世代間のギャップが原因で、おじいちゃん・おばあちゃんが絵本に馴染みにくいという課題が生じているのです。
家族の距離を感じさせる現代の生活スタイル
さらに、家族の距離感も課題のひとつです。
昔は三世代同居が一般的で、日常的におじいちゃん・おばあちゃんが孫の世話をする家庭が多くありました。しかし、核家族化が進んだ現代では、日常的に顔を合わせる機会が少なくなり、おじいちゃん・おばあちゃんと孫の接点も減少しています。
例えば、「孫とどう話していいかわからない」と悩むおじいちゃん・おばあちゃんの声をよく耳にします。一方で、子どもたちも「おじいちゃん・おばあちゃんと何を話せばいいのかわからない」と感じている場合があります。
このような状況が続くと、せっかく家族で過ごす時間があっても、互いに壁を感じてしまうことがあります。
おじいちゃん・おばあちゃんの役割が変化している?
もうひとつ見逃せないのは、おじいちゃん・おばあちゃんの役割の変化です。
現代では、シニア世代の方々も趣味や仕事で忙しい日々を送っていることが多く、「孫のために時間を割く」という意識が薄れていることもあります。
これは悪いことではありませんが、その分、家族間の交流の機会が少なくなっているのも事実です。
そのため、
と悩んでいる声も少なくありません。
このような状況では、孫とのコミュニケーションを取りたい気持ちはあっても、方法が見つからないまま時間が過ぎてしまうことがあります。
解決の糸口は「共有の時間」にあり
これらの課題に共通するのは、「共有する時間」の不足です。
おじいちゃん・おばあちゃん世代と孫世代が同じ時間を共有し、楽しむ機会が少ないため、自然と距離が生まれてしまうのです。
そこで、絵本は大きな可能性を秘めています。世代を超えて一緒に楽しむことができる絵本は、家族の架け橋となりうるのです。
世代を超えて楽しめる絵本の選び方とおすすめポイント

世代を超えて絵本を楽しむためには、どんな絵本を選べばいいのでしょうか?
ポイントは、孫世代とおじいちゃん・おばあちゃん世代の双方に「共感」や「発見」がある内容を選ぶことです。
子ども向けの絵本の中には、大人が読んでも深く考えさせられるものや、懐かしい記憶を呼び覚ます要素を持つ作品がたくさんあります。
以下では、選ぶ際に注目したい条件を詳しく解説します。
1. 懐かしさを感じさせるストーリーやテーマ
おじいちゃん・おばあちゃん世代が特に共感しやすいのは、懐かしさを感じる物語です。
たとえば、日本の昔話や民話を題材にした絵本は、彼らが子どもの頃に親しんだお話を思い出させてくれます。
具体例として、「ももたろう」や「浦島太郎」といった古典的な昔話の絵本は、親しみやすいだけでなく、孫世代に伝えたい文化的な価値も含まれています。
また、動物をテーマにした絵本もおすすめです。
動物の愛らしさや自然との関わりは、どの世代にも共通して響くテーマであり、特に田舎育ちのおじいちゃん・おばあちゃんには懐かしい感情を引き起こすかもしれません。
2. 大人も感動できる深いメッセージ性
最近の絵本には、大人向けの哲学的なメッセージが込められている作品も増えています。
たとえば、【絵本の例:『いちばん星みつけた』や『おおきな木』】などは、シンプルながらも人生や家族愛について考えさせられるストーリーが特徴です。
おじいちゃん・おばあちゃんも一緒に読んで共感しやすく、孫との会話のきっかけにもなります。
こうした絵本を選ぶと、子どもには「わからないけど面白い」、大人には「心に響く」という二重の楽しみを提供できます。
3. 視覚的に読みやすいデザイン
年齢を重ねると視力が衰えるため、小さな文字や色使いの派手すぎる絵本は避けたほうが無難です。
大きめの文字、落ち着いた色合いのイラストが使われている絵本を選ぶと、おじいちゃん・おばあちゃんも読みやすくなります。また、余白が多めで文章量が適切な絵本は、読む側の負担を軽減します。
例えば、『ぐりとぐら』シリーズは、優しいタッチの絵と読みやすい文字サイズが特徴で、幅広い世代に愛されています。
4. 読み聞かせに適したリズミカルな文章
おじいちゃん・おばあちゃんが読み手となる場合、文章がリズミカルで読みやすい絵本を選ぶことも重要です。
韻を踏んだり、語感が良い文章は声に出して読むと心地よく、読み手と聞き手の両方が楽しめます。
具体例として、『だるまさんが』シリーズは、短いフレーズでユーモアたっぷりの内容なので、読み聞かせ初心者のおじいちゃん・おばあちゃんにもおすすめです。
5. 家族の会話が生まれる内容
家族間の会話を引き出す絵本も効果的です。
たとえば、テーマが食べ物や季節のイベントに関連しているものは、「昔はこうだったよね」といった思い出話を引き出すきっかけになります。
『はらぺこあおむし』は、食べ物をテーマにしており、孫世代と世代を超えた会話が自然に生まれる絵本の代表例です。
おすすめの絵本一覧表
以下は、おじいちゃん・おばあちゃん世代と孫世代が一緒に楽しめる絵本の例です。
| 絵本タイトル | 特徴 | 対象年齢 | 価格目安 |
|---|---|---|---|
| 『ももたろう』 | 昔話の定番。世代間で共有できるテーマ | 3歳以上 | 約1,000円 |
| 『おおきな木』 | 人生や家族愛を考えさせる深いメッセージ性が魅力 | 5歳以上 | 約1,200円 |
| 『ぐりとぐら』 | 読みやすい文字サイズと優しいイラストが特徴 | 3歳以上 | 約900円 |
| 『だるまさんが』 | 短いフレーズとユーモアで読み聞かせ初心者にもおすすめ | 1歳以上 | 約850円 |
| 『はらぺこあおむし』 | 食べ物をテーマにした絵本で家族の会話を引き出す | 2歳以上 | 約1,300円 |
適切な絵本を選ぶことは、単に子どもたちを喜ばせるだけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんとの新しいつながりを作る機会にもなります。
お気に入りの絵本が家族の「共通言語」となり、世代を超えた楽しい思い出を生み出す可能性が広がります。
おじいちゃん・おばあちゃんが絵本を読むことのメリット

メリット① 家族の時間を共有できる
絵本を読む時間は、家族の新しい習慣を作るきっかけになります。
たとえば、夜寝る前におじいちゃんが孫に絵本を読んであげる時間ができれば、それは孫にとって特別なひとときになります。
また、絵本を通じておじいちゃん・おばあちゃんの若い頃の話が自然と出てくることもあります。「この話は私が子どもの頃に聞いた昔話だよ」といったエピソードが孫にとって新鮮な学びとなります。
メリット② 教育的な効果がある
絵本を読むことは、子どもの想像力や語彙力を育てるだけでなく、感情を理解し共有する力を高めます。
一方で、おじいちゃん・おばあちゃんにとっても新しい学びがあります。たとえば、最近の絵本は多文化やSDGsのテーマを扱うものが多く、世代を超えて「今」の世界を知る機会になります。
メリット③ 思い出を作ることができる
絵本は単なる読み物ではなく、家族の絆を育む「思い出作り」のツールです。
将来、孫が大人になったときに「おじいちゃんと読んだあの絵本が忘れられない」と語ることもあるでしょう。その思い出が家族全体の絆をより強固なものにします。
メリット④ リラックス効果がある
おじいちゃん・おばあちゃんにとっても、絵本の読み聞かせは心を穏やかにする時間になります。特に感情豊かなストーリーや優しいイラストは、孫と一緒に癒しを共有できる瞬間です。
おじいちゃん・おばあちゃんが絵本を読むことのデメリット

デメリット① 文字が小さく読みづらい
高齢者にとって、小さな文字や目に負担のかかる派手な配色の絵本は読むのが難しいことがあります。
この場合、文字が大きく読みやすい絵本を選ぶことが大切です。また、音声付きの絵本アプリを活用することで、視覚的な負担を軽減することも可能です。
デメリット② 孫との興味のギャップ
子どもが夢中になる内容がおじいちゃん・おばあちゃんにはピンとこない場合もあります。
たとえば、現代的なキャラクターやユーモアが盛り込まれた絵本は、シニア世代にとっては馴染みにくいかもしれません。
この場合、昔話や普遍的なテーマを扱った絵本を選ぶことで、このギャップを埋めることができます。
デメリット③ 声を出して読むことの疲れ
長時間声を出して絵本を読むことは、思った以上に体力を使います。
特に高齢者の場合、声がかすれたり疲れたりしやすいことがあります。この場合は、短い話がいくつか収録された絵本や、読み聞かせ用のCDやアプリを活用してみるのも良いでしょう。
デメリット④ 初めは抵抗感を感じる場合がある
おじいちゃん・おばあちゃんの中には、「子ども向けの本を読むなんて恥ずかしい」と感じる人もいます。
この抵抗感を和らげるためには、孫から「おじいちゃんに読んでほしい」とお願いする形をとると効果的です。孫の純粋なリクエストには自然と応じやすくなります。
メリットとデメリットを解決するための工夫
以下は、おじいちゃん・おばあちゃんが絵本をより楽しめるようにするための具体的な工夫です。
| 課題 | 解決策 |
|---|---|
| 文字が小さく読みづらい | 文字が大きい絵本を選ぶ、タブレットや電子書籍を活用する |
| 孫との興味のギャップがある | 昔話や普遍的なテーマを扱った絵本を選ぶ |
| 声を出して読むことに疲れる | 短編絵本を選ぶ、音声アシストを活用 |
| 抵抗感がある | 孫からのリクエスト形式にする、簡単で楽しい内容から始める |
絵本の時間は、家族が一緒に笑い合い、時には感動し、忘れられない思い出を作る貴重な時間です。メリットを活かし、デメリットを工夫で乗り越えれば、三世代が一緒に楽しむことができるのです。
三世代で絵本を楽しむヒントと今すぐ試したい一冊!

絵本は単なる読み物ではなく、家族の絆を深める「架け橋」としての役割を果たしてくれます。
おじいちゃん・おばあちゃんが孫に絵本を読むことで、家族全員が一緒に笑い、感動し、新しい思い出を作ることができます。世代を超えた共通の話題が生まれ、親世代にとっても、子どもにとっても、そしてシニア世代にとっても特別な時間となるでしょう。
今回ご紹介した絵本選びのポイントやおすすめタイトルを参考に、まずは手に取りやすい一冊から始めてみてはいかがでしょうか?
たとえば、『おおきな木』や『ももたろう』のような普遍的なテーマの絵本は、多くの人にとって心に残る物語です。短い時間でも、声に出して読むことで新しい発見があるかもしれません。
絵本を通じて生まれる会話や感情の共有は、家族全員にとってかけがえのないものです。ぜひ今日から「絵本の時間」を始めてみてください。






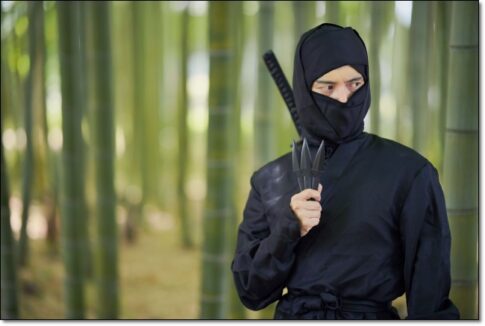
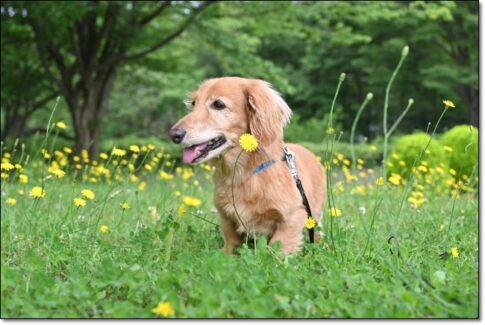








「孫には会いたいけど、何をしていいかわからない」
「子どもがゲームやスマホばかりで話しかけるのが難しい」